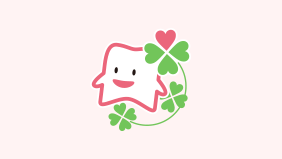歯周病になりやすい人の特徴とは?原因と予防法を徹底解説
無料相談受付中!
お気軽にご連絡ください。
-
\ 電話相談 /
072-762-4618 -
\ メール相談 /
問い合わせ -
\ LINE相談(矯正のみ) /
LINE登録
「毎日ちゃんと歯を磨いてるのに、なぜか歯ぐきが腫れる」
そんなふうに感じたことはありませんか?
実は、歯周病は単なる磨き残しだけが原因ではありません。
生活習慣や体質、さらには全身の健康状態など、複数の要因が複雑に関係して発症する病気です。
そこで本記事では、次のような内容について詳しく解説していきます。
- 歯周病になりやすい人の特徴
- 歯周病の予防方法
「これ、自分にも当てはまるかも?」と思ったら、日頃のケアを見直すチャンスかもしれません。
口の健康は全身の健康にもつながりますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
歯周病になりやすい人の特徴

歯周病になりやすい人の特徴は、以下の3つです。
- 口腔衛生状態が悪い人
- 生活習慣に問題がある人
- その他
順番に解説します。
口腔衛生状態が悪い人
プラーク(歯垢)や歯石に含まれる細菌が増えると、歯ぐきに炎症が起きやすくなります。
とくに歯と歯ぐきの境目は汚れがたまりやすく、放置すると歯周ポケットが深くなりやすいため、丁寧なケアが必要です。
自覚症状がないうちに進行するケースもあるので注意が必要です。
関連記事:歯石はなぜ取るべき?歯石除去が大切な理由と放置するリスク
歯磨きが不十分な人
歯の表面にたまるプラーク(歯垢)は、歯周病の原因菌が集まりやすい場所です。
しっかりと磨けていないと、このプラークが増えていき、歯ぐきの炎症や出血などにつながることがあります。
とくに寝ている間は唾液が少なくなり、菌が活動しやすくなるため、寝る前の丁寧な歯磨きが大切になります。
歯並びが悪い人
歯ブラシが届きにくい場所が増えることで、汚れが残りやすくなります。
その結果、磨き残しが慢性的に生じ、炎症の原因になります。
必要に応じて矯正治療や、磨き方の指導を受けると良いでしょう。
不適合な詰め物や被せ物がある人
段差やすき間に汚れが溜まりやすく、歯ぐきに慢性的な炎症を引き起こします。
詰め物や被せ物が古くなっている場合も、適合性の再確認が必要です。
歯石が多い人
歯石はプラークが石灰化したもので、細菌が常に住みつく温床になります。
歯石の表面はざらついており、さらに汚れが付きやすくなるため、悪循環を生みます。
生活習慣に問題がある人
歯周病は、口の中だけの問題ではありません。
実は、日々の生活リズムや体の状態も大きく関わっています。
偏った食事、睡眠不足、喫煙やストレスの蓄積など、さまざまな生活習慣が歯ぐきにじわじわと影響を与えているのです。
ここでは、歯周病リスクを高める主な生活習慣について見ていきましょう。
喫煙者
喫煙によって歯ぐきの血流が悪くなると、酸素や栄養が届きにくくなります。
その結果、炎症が起きても治りにくく、免疫力も落ちやすくなるのです。
また、出血や腫れなどの変化に気づきにくく、進行しても見逃されやすい傾向があります。
糖尿病患者
糖尿病があると免疫力が下がり、歯ぐきの炎症が治りにくくなります。
血糖値が高いと細菌への抵抗力も弱まり、歯周病が進みやすくなります。
そのため、歯と体の両方を意識したケアが必要です。
ストレスを抱えている人
ストレスはホルモンバランスを崩し、免疫力を下げることで歯周病リスクを高めます。
加えて、睡眠不足や生活の乱れが重なることで、セルフケアの質も落ちがちです。
気持ちに余裕がなくなると、歯科受診のタイミングも遅れやすくなることで、気づかないうちに歯周病が進行してしまうかもしれません。
歯ぎしりや食いしばりがある人
無意識の歯ぎしりや食いしばりは、歯や歯ぐきに余計な力をかけます。
それが炎症や歯のぐらつきの原因になることも。
マウスピースを使い、力の負担を減らす工夫が大切です。
口呼吸をする人
常に口が開いている状態だと口腔内が乾燥しやすくなり、唾液の抗菌作用が働きにくくなります。
結果として、細菌が繁殖しやすくなり、歯周病が進行しやすい環境が整ってしまいます。
甘いものや柔らかいものを好む人
甘いものは歯周病菌のエサになり、プラークの形成を促します。
また、柔らかいものばかりを食べていると噛む回数が減り、唾液の分泌も少なくなります。
唾液には自浄作用があるため、これが不足することで菌が増えやすくなってしまうのです。
不規則な食事や栄養の偏りがある人
栄養バランスが崩れると、歯周組織を維持するのに必要なビタミンCやたんぱく質、カルシウムなどが不足します。
とくにビタミンCはコラーゲン合成に関わるため、不足すると歯ぐきが弱くなってしまうのです。
その他
歯周病には「磨き残し」などの生活習慣だけでなく、年齢・体質・全身の状態が関係していることもあります。
ここでは、特に注意が必要な方の特徴についてご紹介します。
ご自身やご家族に当てはまる項目がないか、チェックしてみてください。
遺伝的要因がある人
両親や兄弟に重度の歯周病経験者がいる場合、体質や免疫機能の影響で歯周病にかかりやすい傾向があります。
定期的なチェックや、早期の対策がより重要になります。
特定の病気を患っている人
骨粗しょう症になると、歯を支える骨ももろくなり、歯周病が進行しやすくなります。
治療薬を服用している方は、抜歯などの処置に注意が必要です。
お口の健康も、骨のケアと一緒に考えることが大切です。
高齢者
加齢により、唾液の分泌が減ったり、歯ぐきがやせたりして、歯周病のリスクは上がります。
入れ歯やブリッジを使っている場合も、清掃が行き届きにくくなりがちです。
長年お口の中を守ってきた方ほど、ここからのケアが大切です。
歯を支える力が弱くなってくるからこそ、丁寧なメンテナンスで支えていきましょう。
妊娠中の女性
妊娠中はホルモンバランスの影響で、歯ぐきが腫れやすくなったり出血しやすくなったりします。
「妊娠性歯肉炎」と呼ばれるこの状態は、一時的なものとはいえ放置は禁物。
妊娠中の歯科受診を不安に思う方も多いですが、安定期であればクリーニングや検診は問題なく行えます。
赤ちゃんのためにも、お口の健康を守っていきましょう。
歯周病の予防法

歯周病の予防方法は、以下の3つです。
- 毎日の丁寧なセルフケア
- 定期的な歯科検診とプロフェッショナルケア
- 生活習慣の改善
それぞれを解説します。
毎日の丁寧なセルフケア
歯周病を防ぐには、正しい方法で丁寧にケアを続けることがとても大切です。
どれだけ毎日歯を磨いていても、自己流のままだと磨き残しが出やすく、歯ぐきの炎症につながってしまうことがあるからです。
「ちゃんと磨いているのに、どうして歯ぐきが腫れるんだろう…」と感じたことがある方もいるかもしれません。
実は、磨く角度・力加減・使う道具によって、結果は大きく変わります。毎日の歯みがきに少し意識を向けるだけで、お口の状態がぐっと変わる可能性があるのです。
だからこそ、正しいセルフケアを知り、実践することが、歯ぐきの健康を守る第一歩といえるでしょう。
正しい歯磨き方法を実践する
歯や歯ぐきを健康に保つには、力まかせに磨くのではなく、やさしく丁寧に磨くことが大切です。
強くこすると、かえって歯ぐきを傷めてしまうこともあります。
歯ブラシは、ペンのように軽く持って、なでるように動かしてみてください。
磨く場所も意識が必要です。
歯の表面だけでなく、奥歯のかみ合わせや歯と歯の間など、汚れがたまりやすいところをていねいに。
歯ブラシは、毛先がやわらかくてヘッドが小さいものがおすすめ。細かいところまで届きやすくなります。
「ちゃんと磨いてるのに」と感じたときこそ、毎日のケアを少しだけ見直すタイミングなのかもしれません。
デンタルフロスや歯間ブラシの活用
実は、歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れを完全に落とすのは難しいんです。
届きにくい場所のプラークは、歯ブラシだけだと半分くらいしか取れないとも言われています。
だからこそ、歯間ブラシやデンタルフロスをプラスして使うことが大切になってきます。
歯間ブラシを使うときは、歯のすき間の大きさに合ったサイズを選ぶのがポイントです。
無理に入れようとすると歯ぐきを傷つけてしまうこともあるので、ぴったりのサイズを見つけて使ってください。
デンタルフロスは、力を入れすぎず、ゆっくりと歯の間に通してみましょう。
そのあと、フロスを歯の横に沿わせながら、やさしく汚れをぬぐい取るように動かすと効果的です。
洗口液の利用
歯みがきが不十分になりそうな日には、洗口液を活用してみましょう。
疲れているときは、つい磨きが雑になってしまうこともあります。
そんなときに殺菌作用のある洗口液を使うことで、細菌の増殖を抑える手助けになります。
毎日でなくても構いません。無理のない範囲で取り入れることが、お口の健康を守る一歩になります。
定期的な歯科検診とプロフェッショナルケア
毎日のセルフケアだけでは落としきれない汚れや、見つけにくいトラブルがあります。
歯科医院での定期的なチェックと専門的なクリーニングが、歯周病予防には欠かせません。
歯石除去
歯石は一度つくと、歯ブラシでは落とせません。歯科医院で専用の器具を使って取り除いてもらいましょう。
これを怠ると、どんなに毎日磨いていても歯周病は防ぎきれません。
PMTC
バイオフィルム(細菌の膜)を、専用の器械と研磨剤で丁寧に除去します。
仕上がりはツルツルになり、汚れが再びつきにくくなる効果も期待できます。
歯の表面を健康に保つために、定期的なPMTCはおすすめです。
歯周病のチェック
歯ぐきの検査やレントゲンで、炎症や骨の状態を確認してもらいましょう。
自分では気づかないうちに進行しているケースも少なくありません。
定期的にチェックを受けることで、早期発見・早期対策が可能になります。
生活習慣の改善
どんなに丁寧に歯を磨いていても、生活習慣の乱れが歯周病を進めてしまうことがあります。
実は、食事・ストレス・睡眠・持病の管理など、毎日の暮らしが歯ぐきの状態に大きく影響しているのです。
ここでは、歯周病予防のために見直したい生活習慣をいくつかご紹介します。
禁煙
タバコを吸っていると、歯ぐきの血流が悪くなり、炎症に気づきにくくなります。
歯周病が悪化しやすく、治りにくくなることもわかっています。
今からでも禁煙に取り組むことで、お口の健康は大きく変わります。
バランスの取れた食事
栄養不足は免疫力の低下につながり、歯ぐきの炎症を悪化させる原因になります。
特にビタミンCやタンパク質は、健康な歯ぐきを維持するのに欠かせません。
偏りなく、いろいろな食品を取り入れる意識が大切です。
糖分の摂取を控える
甘いものを頻繁に摂ると、歯垢(プラーク)が増え、歯周病のリスクも上がります。
とくに「だらだら食べ」は細菌のエサを長時間与えてしまうので要注意です。
間食は時間を決めて、回数や内容を見直すことから始めてみましょう。
ストレス管理
ストレスが続くと免疫の働きが低下し、体はもちろん歯ぐきにも悪影響を及ぼします。
さらに歯ぎしりや食いしばりの原因にもなり、歯の根元が削れることもあるのです。
リラックスできる時間や、自分なりの対処法を持っておくと安心でしょう。
全身疾患の管理
高血圧、糖尿病、腎疾患などがあると、歯ぐきの炎症が慢性化しやすくなります。
血糖コントロールがうまくいかないと、歯周病が治りにくくなることもあります。
医科と歯科の両面から健康を見直すことが、予防の第一歩です。
関連記事:大人が歯を失う原因の第1位は?ランキング形式で紹介
まとめ

歯周病は、「気づいたときには進んでいた」というケースが少なくありません。
痛みや腫れがないまま静かに進行していくため、気づいた頃にはすでに歯ぐきや骨にダメージが及んでいることも。
けれど、だからといって怖がる必要はありません。
毎日のセルフケアを見直し、定期的に歯科を受診することで、進行を防ぎ、健康な状態を長く保つことは十分に可能です。
お口の健康は、食事・会話・笑顔など日々の暮らしすべての土台になります。
さらに近年では、歯周病が全身の健康と深く関わっていることも明らかになってきました。
自分のために、家族のために。
今日からできる小さなケアを、少しずつでも取り入れていきましょう。
将来のお口の健康が、きっと変わっていきます。
無料相談受付中!
お気軽にご連絡ください。
-
\ 電話相談 /
072-762-4618 -
\ メール相談 /
問い合わせ -
\ LINE相談(矯正のみ) /
LINE登録

コラム監修者
- はぴねす歯科・矯正歯科 石橋駅前クリニック 総院長 野澤 修一
- 福岡歯科大学を卒業後、福岡県・大阪府・兵庫県の歯科医院にて14年間勤務。その後、2014年9月に「はぴねす歯科石橋駅前クリニック(大阪府池田市)」、2018年6月に「緑地公園駅前クリニック(大阪府府中市)」、2020年7月に「川西能勢口駅前クリニック(兵庫県川西市)」、2022年11月に「尼崎駅前クリニック(兵庫県尼崎市)」を開院。現在は医療法人はぴねすの理事長として4医院を運営。