歯茎がムズムズするのはなぜ?原因と対処方法を紹介
無料相談受付中!
お気軽にご連絡ください。
-
\ 電話相談 /
072-762-4618 -
\ メール相談 /
問い合わせ -
\ LINE相談(矯正のみ) /
LINE登録
「歯茎がムズムズして気になるけど、これって病気なのかな?」と不安に感じていませんか?
「痛みがないからといって放置していても大丈夫なのか」「子育てや仕事で忙しくて歯医者に行く時間がないけど、自宅で何かできることはないか」と悩んでいる方も多いですよね。
歯茎がムズムズするのは、歯周病などの病気の初期症状である可能性があります。
しかし、原因を正しく理解し適切な対処を行えば、症状の改善や予防は十分可能です。
そこで、今回は以下の内容について解説します。
- 歯茎がムズムズする原因と治療方法
- 自宅でできる対処法
- 歯茎のムズムズ感を放置することのリスク
この記事を読むことで、歯茎がムズムズする原因や対処法について正しい知識を理解し、適切な予防法を実践できるようになります。
歯茎のムズムズ感で悩んでいる方や、将来の口腔トラブルを防ぎたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
歯茎がムズムズする原因とは
歯茎がムズムズする原因としては、次のようなものが考えられます。
- 歯周病
- 虫歯
- 親知らず(智歯周囲炎)
- 歯ぎしり・食いしばり
- アレルギー
- 歯肉炎
- ドライマウス
- ホルモンバランス変化
- 被せ物の不具合
- ストレス
一つずつ解説していきます。
歯周病
歯茎がムズムズする症状が現れた場合、その原因の大半は歯周病の初期症状です。
歯周病は歯の周りを支えている骨を溶かす病気で、歯と歯茎の境目にプラーク(歯垢)が蓄積して炎症が生じることで発症します。
歯茎に炎症が生じると、歯茎が腫れ、ムズムズとした違和感やかゆみが現れます。
初期段階では痛みを伴わないことが多いですが、放置すると徐々に症状が悪化し、最終的には歯が抜け落ちる危険性があるので注意が必要です。
虫歯
歯茎がムズムズする原因の2つ目は、虫歯です。
虫歯には段階があり、進行具合によって症状は異なります。
初期虫歯(C1~C2)
初期虫歯は痛みが出る前の段階で、歯茎にムズ痒さを感じることがあります。
虫歯によってできた小さな穴に食べカスが詰まることで、細菌が繁殖して周辺の歯茎が炎症を起こすためです。
初期虫歯の段階で強い痛みはありませんが、冷たいものがしみたり、歯茎に違和感を感じることがあります。
進行虫歯(C3~C4)
進行虫歯でも、歯茎がムズムズすることがあります。
進行虫歯は細菌が神経に達して炎症を起こしている状態で、夜も眠れないほどの激しい痛みが生じます。
根管治療(神経を取る治療)や抜歯が検討される場合も多く、症状が軽いうちの治療が必要です。
根管治療後の歯
根管治療後に根尖性歯周炎が発症して、歯茎がムズムズすることがあります。
根尖性歯周炎とは、歯の根の先端にまで炎症が及び、周囲の歯周組織にも影響が広がっている状態のことです。
一度根管治療を受けた歯でも、根の構造が複雑で細菌を完全に取り除けなかったり、治療から時間が経つことで被せ物が劣化したりすることがあります。
そして、歯と被せ物の隙間から細菌が侵入することで、再び感染を引き起こしてしまうのです。
親知らず(智歯周囲炎)
親知らず周辺の歯茎がムズムズする場合、智歯周囲炎の可能性があります。
親知らずは斜めや横向きに生えることが多く、歯ブラシが届きにくい位置にあるため、歯垢や食べカスが非常に溜まりやすいです。
この汚れが原因で細菌が繁殖し、親知らず周辺の歯茎に炎症が起こります。
初期段階では軽いムズムズ感や腫れ程度の症状ですが、進行すると強い痛みや口が開けられない状態まで悪化することもあります。
歯ぎしり・食いしばり
歯ぎしりや食いしばりが原因で、歯茎がムズムズすることがあります。
強い力が歯に継続的に加わることで、歯と顎の骨をつなぐ歯根膜という組織に過度な負担がかかり、炎症を起こすためです。
この状態を歯根膜炎といい、初期症状として歯茎のムズムズ感や歯が浮いたような違和感が現れます。
アレルギー
歯茎がムズムズする原因として、「金属アレルギー」と「口腔アレルギー症候群」が考えられます。
金属アレルギー
歯科では、パラジウム合金という金属を銀歯の材料として使っています。
パラジウム合金はアレルギー反応を引き起こしやすい材料として知られており、口腔内のムズムズ感や炎症を引き起こす原因になります。
唾液などの影響で金属が少しずつ溶け出し、突然、金属アレルギーの症状が出ることもあるため注意が必要です。
口腔アレルギー症候群
口腔アレルギー症候群は特定の果物や生野菜を食べた直後に、口の中や喉のかゆみ、しびれ、むくみなどが現れる疾患です。
多くの場合は時間と共に自然に回復しますが、まれにアナフィラキシーなど重篤な反応を起こすことがあります。
歯肉炎
歯肉炎は、歯茎がムズムズする代表的な原因の一つです。
歯と歯茎の境目に蓄積されたプラーク(歯垢)や歯石に含まれる細菌が歯茎に炎症を起こすことで発症します。
初期の歯肉炎では痛みよりもムズムズとした違和感や軽いかゆみを感じることが多く、歯磨き時に出血することもあります。
ドライマウス
口内が乾燥して唾液分泌量が減少すると、細菌が繁殖しやすくなり、歯茎に炎症を起こします。
炎症や乾燥した環境によって歯茎が敏感になり、違和感やムズムズした感覚が現れることがあります。
ドライマウスは、加齢、薬の副作用、ストレスによって引き起こされることが多いです。
ホルモンバランス変化
妊娠中や更年期などホルモンバランスが変化する時期は、歯茎が影響を受けやすく、ムズムズ感が現れることがあります。
これは女性ホルモンの分泌が増えることで、毛細血管が影響を受け、炎症反応が強く出やすくなるためです。
特に歯周病の原因菌の中には女性ホルモンを好む種類があり、ホルモンレベルの上昇と共に細菌が繁殖しやすくなります。
被せ物の不具合
被せ物の不具合は、歯茎がムズムズする原因となります。
被せ物と歯の間に隙間があると食べカスが詰まりやすくなり、細菌が繁殖して歯茎に炎症を起こすためです。
また、合っていない被せ物は歯ブラシやフロスが引っ掛かりやすく、歯茎を傷つけてムズムズとした不快感を生じさせることもあります。
ストレス
ストレスは、歯茎がムズムズする大きな原因の一つです。
精神的な疲労やストレスが蓄積すると、自律神経の働きが乱れて唾液分泌量が減少し、口腔内が乾燥しやすくなります。
唾液には殺菌作用や口腔内の洗浄・保湿機能があるため、これが不足すると細菌が繁殖しやすくなり、歯茎に炎症が起こります。
歯茎がムズムズする原因別の治療方法
歯茎がムズムズする原因はさまざまですが、それぞれに適した治療法があります。
- 歯周病治療
- 虫歯治療
- 親知らず抜歯
- 被せ物の調整
- アレルギー治療
- ストレスケア
これから原因別の治療方法を紹介します。
歯周病治療
歯周病の治療は、根本原因である歯垢や歯石を除去することから始めるのが基本です。
歯科医院にある専用の器具を使って、歯と歯茎の隙間に潜む細菌を徹底的に除去します。
症状の進行具合によっては、レーザーや薬による除菌処置が行われることもあります。
早期に対処するほど歯を守れる可能性が高まるため、できるだけ早く歯科医院を受診しましょう。
虫歯治療
虫歯の治療は、虫歯の進行度に応じて異なるアプローチが必要です。
初期虫歯の場合は、正しい歯磨きとフッ素塗布によって治すことも可能です。
神経に達した虫歯の場合は、根管治療により感染した神経を除去し、その後被せ物で修復します。
虫歯の穴を塞ぐことで食べカスが詰まらなくなれば、細菌の繁殖も抑えられるため、歯茎のムズ痒さも改善されるでしょう。
親知らず抜歯
智歯周囲炎の治療として、親知らずの抜歯が必要になることがあります。
親知らずが斜めや横向きに生えている場合、清掃が困難で繰り返し炎症を起こしやすいためです。
抜歯は局所麻酔下で行われ、まっすぐ生えた親知らずなら比較的簡単に済みます。
しかし、深く埋まっていたり横向きの場合は歯茎を切開し歯を分割する必要があり、術後1週間程度の腫れや痛みを伴うことがあります。
被せ物の調整
被せ物の不具合の治療には、適切な調整措置が必要です。
歯科医師に噛み合わせの高さや形状を確認してもらい、フィットする被せ物に調整しましょう。
被せ物と歯の隙間から細菌が侵入して歯茎に炎症を起こしているため、フィット感の改善が症状軽減につながります。
被せ物の下で虫歯が進行している場合は、その治療も同時に行われます。
アレルギー治療
アレルギーの治療は、原因となるアレルギーの特定と除去が基本です。
金属アレルギーが疑われる場合は、アレルギーの原因である金属を除去し、セラミックやジルコニア、レジンなどの材料に変更してみてください。
口腔アレルギー症候群の場合は、内科やアレルギー科を受診し、原因となる食品の摂取を避けることが基本的な対処法となります。
症状が現れた際には、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬による対症療法を行いましょう。
ストレスケア
ストレスによる歯茎のムズムズ感の治療には、日常的なストレス管理が必要です。
十分な睡眠時間を確保する、お風呂にゆっくり浸かる、軽めの運動やストレッチを習慣化するなど、ストレス解消に効果的な方法を実践しましょう。
規則正しい生活リズムを保つことで自律神経のバランスが整い、症状の軽減が期待できます。
継続的なケアにより心身ともに健康な状態を維持することが重要です。
歯茎がムズムズする時の対処方法
原因別の治療法があるとはいえ、仕事や家事で忙しく、歯科医院の受診が難しいという方もいますよね。
そこで、自宅でもできる対処法を紹介します。
対処方法としては、主に次の3つです。
- 正しい歯磨きをする
- うがい薬を使用する
- ストレスを解消する
順番に解説します。
正しい歯磨きをする
歯茎がムズムズする時の対処法として、毎日のブラッシング方法を見直すことが最も効果的です。
まず、歯ブラシは硬すぎると歯茎を傷つけるため、柔らかめのものを選びましょう。
ブラシは45度の角度で歯茎に当て、小刻みに優しく動かすのがポイント。
また歯間ブラシやデンタルフロスも併用し、歯と歯の間の汚れをしっかり除去してください。
1日に最低でも2回以上、1回につき3分程度時間をかけて丁寧に磨くことで、歯茎の炎症が抑えられ、ムズムズ感の軽減につながります。
うがい薬を使用する
うがい薬は、歯茎がムズムズするのを一時的に緩和する手軽な対処法としておすすめです。
うがい薬で歯や歯茎をすすぐことで、殺菌成分が口腔内の細菌を減らし、歯茎の炎症を抑えることができます。
歯磨きと共に毎日の習慣として取り入れることで、口腔環境の改善が期待できるでしょう。
ストレスを解消する
ストレスの蓄積は歯茎のムズムズ感を悪化させる要因となるため、日常的なストレス管理が重要です。
忙しい育児や仕事の合間でも、5分程度の瞑想や好きな音楽を聴くなど、自分なりのリフレッシュ方法を見つけましょう。
ストレス管理や規則正しい生活リズムを整えることで、体の免疫機能が正常に働き、歯茎の健康状態も改善されやすくなります。
歯茎がムズムズする症状を放置するリスク
歯茎がムズムズする症状を放置してしまうと、次のようなリスクがあります。
- 歯周病の進行や歯の喪失リスク
- 口臭や見た目への影響
- 全身疾患(糖尿病・心疾患など)
最悪な未来を避けるためにも、しっかりリスクを把握していきましょう。
歯周病の進行や歯の喪失リスク
歯茎がムズムズする症状を放置すると、最悪の場合、歯周病が進行して大切な歯を失う危険性があります。
歯周病は「静かなる病気」と呼ばれ、初期段階では目立った症状はありません。
ただ、気付かないうちに炎症が歯茎の奥深くまで広がっていき、歯を支えている歯槽骨という骨が徐々に壊れていきます。
骨が破壊されると歯がグラグラと動き始め、最終的には自然に抜け落ちる可能性が高いです。
歯を失うと噛む力が低下し、食事の楽しみが減るだけでなく、隣接する歯にも負担がかかり口腔内全体のバランスが崩れてしまいます。
早めの対処で、このような深刻な事態を防ぐことが大切です。
口臭や見た目への影響
歯周病が進行すると歯周ポケットに細菌が増殖し、口から強い悪臭が発生します。
口臭は自分では気づきにくいものの、他人には明らかに分かる不快な匂いになることもあります。
また、歯茎が腫れて赤くなったり、出血や膿が出たりすることで、周囲とのコミュニケーションにも支障をきたし、人間関係にまで悪影響を及ぼす可能性が高いです。
日常生活への悪影響を避けるためにも、早めに歯科医師に相談しましょう。
全身疾患(糖尿病・心疾患など)
歯茎がムズムズする症状を軽視すると、将来的に糖尿病や心疾患などのリスクが高まる可能性があります。
歯周病菌や炎症性物質が血流を通じて全身に運ばれることで、様々な臓器に悪影響を与えるためです。
特に糖尿病との関係は密接で、歯周病があると血糖値のコントロールが困難になることが研究で明らかになっています。
口の中の小さな炎症が、命に関わる重大な病気につながる恐れがあるのです。
家族の健康を守るためにも、早期の対処が欠かせません。
まとめ
歯茎がムズムズする原因を正しく理解し適切な対処を行えば、症状の改善や予防は十分可能です。
違和感がある場合は自分で判断せず、歯科医師に診てもらいましょう。
しかし、すぐに受診できない場合は、正しい歯磨きやうがい薬の使用、ストレス解消などの自宅でできる対処法を実践することをおすすめします。
早期対処をすることで、症状が改善し、健康な口腔環境を維持できる可能性は高くなります。
歯茎のムズムズ感に悩んでいる方は、本記事で原因や対処法について正しい知識を取り入れ、適切な予防法を実践できるようになってください。
無料相談受付中!
お気軽にご連絡ください。
-
\ 電話相談 /
072-762-4618 -
\ メール相談 /
問い合わせ -
\ LINE相談(矯正のみ) /
LINE登録

コラム監修者
- はぴねす歯科・矯正歯科 石橋駅前クリニック 総院長 野澤 修一
- 福岡歯科大学を卒業後、福岡県・大阪府・兵庫県の歯科医院にて14年間勤務。その後、2014年9月に「はぴねす歯科石橋駅前クリニック(大阪府池田市)」、2018年6月に「緑地公園駅前クリニック(大阪府府中市)」、2020年7月に「川西能勢口駅前クリニック(兵庫県川西市)」、2022年11月に「尼崎駅前クリニック(兵庫県尼崎市)」を開院。現在は医療法人はぴねすの理事長として4医院を運営。
医療法人はぴねすグループリンク
-

- 尼崎の歯医者
はぴねす歯科・矯正歯科
尼崎駅前クリニック - 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-2-1 ローレルコート・クレヴィア3F
TEL 06-6497-4618
- 尼崎の歯医者
-

- 豊中市緑地公園の歯医者
はぴねす歯科
緑地公園駅前クリニック - 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-13-57
TEL 06-6151-4618
- 豊中市緑地公園の歯医者
-

- 川西能勢口の歯医者
はぴねす歯科
川西能勢口駅前クリニック - 〒666-0033 兵庫県川西市栄町1-19 ♭KAWANISHI102
TEL 072-757-4618
- 川西能勢口の歯医者
-
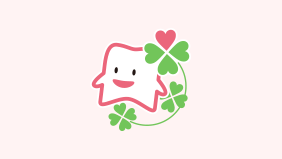
- 吹田市南千里の歯医者
はぴねす歯科・矯正歯科
南千里駅前クリニック - 〒565-0862 大阪府吹田市津雲台1-1-30 トナリエ南千里2階
TEL 06-6318-5004
- 吹田市南千里の歯医者


